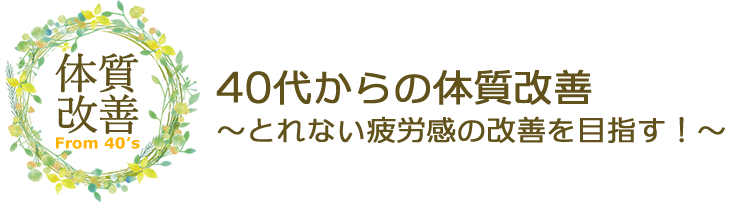マヌカハニーと同様の健康効果が期待できると、最近じわじわと人気のでているマリーハニーやジャラハニー。
最近その存在を知ったのでチェックしてみると、特にマリーハニーはお手頃価格!
マヌカハニーはUMFやMGOなどしっかりした基準があり、安心感がありますが、家族みんなで食べようと思うと、高くてお値段が気になるところ…。
すっかりブランド化したマヌカハニーと同様の効果があるなら、ほかのハチミツでもいいかもと思い興味を持ちました。
薬だったら、後発医薬品のジェネリック医薬品があるし、同様の効果のものが何らかの理由で安い場合があってもおかしくはないですよね。
そう思って調べてみたら、マヌカハニーと他のはちみつの明らかな違いがありました。
それらをまとめてみました。
マリーハニーやジャラハニーとマヌカハニーの違いは?
マリーハニーやジャラハニー。
これらは、「マヌカハニーと同様の効果を持つ」や「マヌカハニーと同様の健康活性力」、「マヌカハニーと同様の検査方法での証明書付き」などと謳われ販売されています。
ちょっとマヌカハニーの知識がある場合、UMFやMGOなどの基準と同等なのかな?と期待してしまいますよね。
ちなみに、UMFやMGOというのは、マヌカハニーの抗菌活性力を示すための評価基準であり、ブランドマークになります。
マヌカハニーを選ぶ時、この2種類のマークがついているものを選べば、偽物をつかまされることはないだろうといえるブランドマークです。
UMFやMGOについては、↓の記事に詳しく書いています。

では「マリーハニーやジャラハニーは、本当にマヌカハニーと同様の効果があるのか」について詳しく説明します。
マリーハニーやジャラハニーとマヌカハニーは評価基準が違った!
ネットショップなどで販売されているマリーハニーやジャラハニーと、本物のマヌカハニーは検査の仕方や評価基準が違います。
【マヌカハニー 】
UMFやMGOなどで表記されている。
MGO(メチルグリオキザール)というマヌカハニーの抗菌成分の量や濃度で
抗菌レベルがわかる。
参考:UMFとMGOの数値の対応表の一部
UMF5+=MGO83+、UMF10+=MGO263+、UMF15+=MGO514+
※MGO表記の商品は、MGO250+やMGO400+などときりのいい数値で
表記されています。
【マリーハニー・ジャラハニー】
TA(トータルアクティビティー検査)での結果を表記。
TA20+やTA30+などと表記されている。
これを見ると、検査方法が違うのがわかります。
この検査基準がどう違うのかについて、これから解説します。
補足:ここで「本物のマヌカハニー」と表現したのは、TA基準で表記されているものや、特に何も書いていないマヌカハニーがあるからです。
マヌカハニーには、UMFやMGOなどのブランドマークがついていない、MGOによる抗菌効果の有無がわからないものもあるので、ご注意ください。
UMFやMGOとTAの違いは?
まず、UMFとMGOについては、以下になります。
【UMF】
UMFとはマヌカハニーの基準値を示すために生まれた最初のブランドマークです。
マヌカハニー研究の第一人者であるピーター・モラン博士が1998年に定めた規格で
もっともポピュラーな規格といっても良いでしょう。「Unique Manuka Factor」の略で「マヌカハニーの独特な要素」という意味を
持っています。UMFはマヌカハニーの抗菌成分濃度を計測したものです。
UMFはニュージーランド政府が100%出資している検査機関で厳しく検査され
合格したものにしか表記されません。すなわちこの表記がついているマヌカハニーは政府が認めた正規品ということなのです。
【MGO】
これは、2008年にドレスデン工科大学のトーマス・ヘンレ教授が発見した、マヌカハニーの主成分「メチルグリオキサール(MethylGlyOxal)」の略です。
そしてMGOは、この抗菌作用を持つメチルグリオキサールの含有量を示すもので、マヌカハニーの中に何mgのメチルグリオキサールが含まれているかを計測します。
MGOは、UMFよりも厳密な検査がされており、正確な品質を保証するともいわれているようです。
UMFについて
UMFとは、マヌカハニー特有の抗菌成分の濃度を数値化したものです。
当時は、それが「メチルグリオキサール(MethylGlyOxal)」だと解明されていなかったため、マヌカハニーの抗菌強度を一般の殺菌剤であるフェノール液と比較する事で数値化しました。
例えばUMF10+は、10%濃度のフェノールと同じ殺菌力があることを意味します。
また、数値が高くなるほど、殺菌力も高まります。
MGOについて
MGOは、メチルグリオキサールが1kgあたり何mg含まれているかを示しています。
これらを見ると、UMFもMGOもメチルグリオキサールという成分に対しての指標であることが分かります。
TAについて
UMFやMGOに対して、TAは以下になります。
「All About マヌカハニー」を参考にさせていただきました。
【TA(トータルアクティビティー検査)】
マヌカハニーだけでなく、その他の蜂蜜にも用いられる検査基準です。
マヌカハニーのUMFやMGOのように、「メチルグリオキサール」という抗菌成分以外の
抗菌成分も含めての数値になります。
普通の蜂蜜に含まれる抗菌成分「過酸化水素」と「メチルグリオキサール」を合わせた
殺菌力が数値化されています。
TAは、メチルグリオキサール単体での成分の表示ではないというのが、UMFやMGOとの一番の違いになります。
UMF、MGO、TAの評価基準について
これらの評価基準が、実際にどう数値化されるのかを例にあげてみます。
TAは、UMFと同じく比較等級法の検査を行い、黄色ブドウ球菌への殺菌力が同濃度の消毒薬のフェノールと同じ効果があるかを調べます。
例えば、あるマヌカハニーに含まれる抗菌力が食品メチルグリオキサール(以下MGO)を10+、過酸化水素(以下HP)を10+とすると、UMF規格はMGOのみを示すため10+と表記されますが、TAではMGO+HPの抗菌力を示すため20+と表記されます。
たとえば、上の説明を具体例に表すと以下のようになります。
MGOが10+、HPが10+の場合
⇒ UMF規格の場合、『UMF10+』と表記。
⇒ TA基準の場合、 『TA20+』と表記。
MGOが5+、HPが15+の場合
⇒ UMF規格の場合、『UMF5+』と表記。
⇒ TA基準の場合、 『TA20+』と表記。
MGOが15+、HPが5+の場合
⇒ UMF規格の場合、『UMF15+』と表記。
⇒ TA基準の場合、 『TA20+』と表記。
どれもTA基準だと『TA20+』なのですが、「メチルグリオキサール」の効果を期待する場合、『TA20+』という表記からは、どれが効果が高いのかがわかりません。
でも、TA基準もはちみつの抗菌効果が数値化されているんだから、同じ抗菌効果さえあれば、「メチルグリオキサール」の割合が多かろうが少なかろうが、ぶっちゃけどっちでもいいよねと思いました。
TA基準では、「過酸化水素」と「メチルグリオキサール」をあわせた殺菌力が数値化されています。
でも、マヌカハニーは「メチルグリオキサール」単体の抗菌効果を指標としているのは、どうしてなのか?
「過酸化水素」の抗菌効果は、「メチルグリオキサール」の抗菌効果とは、質が違うのか?
違うのであれば、どう違うのかが気になります。
そんな疑問がわいてきたので、「過酸化水素」と「メチルグリオキサール」について調べてみました。